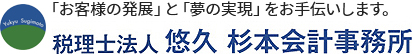改正前を適用した年末調整のその後
基礎控除等の改正適用前に行った年末調整のその後について、概要を確認します。
令和7年分の年末調整では、令和7年度税制改正により次の項目が見直されます。
- 基礎控除
本則 合計所得2,350万円以下の場合控除額が10万円引上げられて58万円
特例 合計所得が655万円以下の場合、合計所得金額に応じて最大37万円を加算(居住者に限る)
- 給与所得控除
最低保障額が10万円引上げ
- 特定親族特別控除
19歳以上23歳未満の一定の親族等を有する場合、その親族等の合計所得金額に応じて最大63万円を控除(居住者に限る)
- 扶養親族等の所得要件
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引上げ
これら基礎控除等の改正は令和7年分からの適用となりますが、年末調整では令和7年12月1日以後から適用します。そのため年末調整の時期により次のように異なります。
年末調整の時期 基礎控除等の適用
(その年の最後の給与支給日)
令和7年11月30日以前 → 改正前
令和7年12月1日以後 → 改正後
改正前を適用した年末調整のその後
死亡等により退職した場合や、海外転勤等により非居住者となること等が原因で、年の途中で改正前の基礎控除等を適用して年末調整を行った場合には、その後、給与の支払を受けた人が改正後の適用を受けるには、確定申告等をする必要があります。この場合の手続きのポイントは主に次の通りです。
- 死亡による退職の場合
死亡による退職を理由に年末調整を行った場合、その後に改正後を適用するには、その死亡した方の相続人等が手続きを行います。
- 非居住者となる場合
海外転勤等により非居住者となることを理由に年末調整を行った場合には、その後において改正後を適用するための手続きを非居住者である間に行うときは、納税管理人を選任する必要があります。
なお、令和7年は1年を通じて非居住者である場合に、納税管理人を通じて令和7年分の確定申告を行うときに適用できる基礎控除は、前述の本則のみになります。加算特例は居住者のみ適用できるため、その年中に居住者期間がなければ適用できません。これは、特定親族特別控除についても同様です。
また、予定納税の減額申請についても注意が必要です。所得税の予定納税は通常、7月と11月の2回、いずれも改正適用前に期限が到来します。このような場合に減額申請を行う際の計算は改正前によることとなりますのでご注意ください。
このように、年末調整を行う時期に応じて基礎控除等の適用額が変わってまいります。ただし改正後の適用が受けられないわけではなく、確定申告等により適用を受けることができます。また、個人事業者等における準確定申告についても同様の取扱いとなります。しかし準確定申告の場合、令和7年12月1日から令和12年12月2日までに更正の請求をすることによって改正後の適用を受けられるようになる点に注意が必要です。
令和7年度の所得税の改正は複雑な部分が多数あります。疑問点やご不安な点等ございましたら、いつでもご相談くださいませ。
参考: 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)」
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第二課 監査担当 大西純平